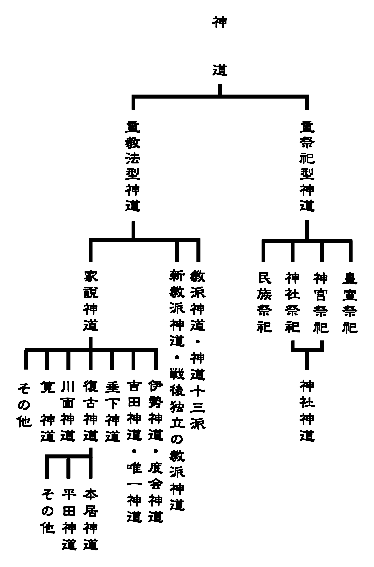神道史(第一回) |
神道の歴史 |
|
神道の歴史は日本の歴史に等しく、同時に日本宗教史の太宗でもある。ただ、神道史と区分した時には、日本宗教史のなかでは特殊な分類とする事に多くの批判は無いだろう。それは、神道の発生と形態に著しく宗教と言い難い部分を包括しているからであり、それが神道を理解しにくくしている原因でもある。 そこで本稿では、まず神道史の区分分けと諸神道の分類をおこない、神道の発生と定義という部分から解説を勧めていきたいと思う。そして、各区分ごとに特徴的なテーマを設定して追いかけていくことで、神道の歴史を体系的に理解していただけることと思う。
|
神道史の区分分け |
|
神道史上の区分分けは、前述の安津素彦師の「神道思想史」に準拠して、以下の如くに分けていく。 第一期 原初信仰時代 第二期 神道仏教関係時代 第三期 教学(学派)神道の成立と展開の時代 第四期 国家神道と教派神道の成立と発展の時代 第五期 神社の宗教化と新教派神道の成立時代
|
|
|
神道の定義 |
|
現在神道は「シントウ」と澄音で訓読されるのが慣例とされている。一宗教教団として成立している教派神道のなかには 「ジンダウ」「シンダウ」と濁音で発声しているところもあるが一部と考えて良い。ローマ字では「SHINTO」と書く。この読みが定まったのは、かなり近年になってからのことであるが、そもそも「神道」という文字が歴史上に最初に見られるのは、中国古典の「易経」にあることは有名である。 観天之神道 而四時不○ 聖人以神道設教 而天下服矣 (天ノ道ヲ観ルニ 四時○ハズ 聖人神道ヲ以ッテ教エヲ設ケテ 天下矣服ス) ここで使われている「神道」は、聖人達徳の人が説く天地自然の理の意味であり、宗教的な「神」のことではない。国内での文献で最初にでてくるのは、かの日本書紀である。 天皇信佛法尊神道 用明天皇記 (天皇ハ仏法ヲ信ジ神道ヲ尊ブ) 天皇…尊佛法軽神道 斯生国魂社樹之類是也 孝徳天皇記 (天皇…仏法ヲ尊ビ神道ヲ軽ンズ 斯ク生国魂社ノ樹之類ガ是也) |